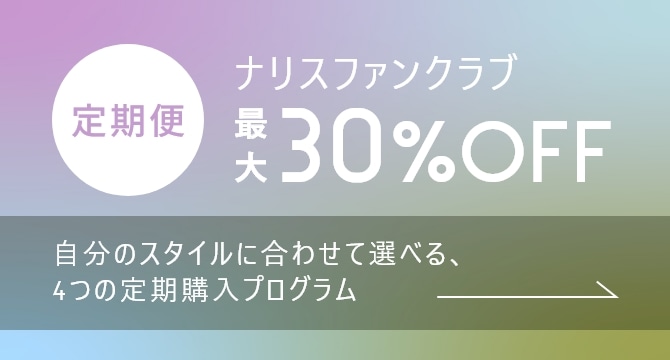人生には理由がある
vol.010 杜氏 / 吉田真子さん
吉田真子 / 杜氏
頑張りすぎない努力で、壁を乗り越える
杜氏 / 吉田真子さん
YouTube

酒蔵に生まれるも酒造りとは無縁
吉田酒造では、毎年秋になると東北から酒造り集団「南部杜氏」を迎え、朝早くから夜遅くまで蔵で酒造りが行われ、杜氏と蔵人※2たちは吉田さん一家と寝食を共にしていました。そんな酒造りが身近で行われていた環境でしたが、酒蔵は神聖な場所というイメージがあったため、吉田真子さんと姉の祥子さんは子どもの頃から蔵に足を踏み入れたことはなかったと言います。
吉田真子さんは酒造りに関わることがないまま高校を卒業し、大阪の大学に進学。卒業後はそのまま関西の企業に就職することを考えていましたが、父・智彦さんの体調がすぐれなかったことから吉田酒造の現社長である母・由香里さんから福井に戻って蔵を手伝って欲しいと頼まれます。当時祥子さんは東京での仕事が軌道に乗っていたこともあり、吉田真子さんはそれならと実家に帰ることを決めました。
※2 蔵人(くらびと):杜氏のもとで日本酒造りに従事する人

「帰ったものの、酒造りの知識もなければ社会人経験もなく、日本酒を飲んだ事すらほぼなかったので何をすればいいか分かりませんでした。営業ならできるかもしれないと考えていましたが、母から営業をするにしても、知識が必要だからまずは酒造りを覚えて欲しいと言われました」
ところが、蔵人として働き始めたその年の冬に智彦さんは54歳という若さで逝去。さらにその後、吉田酒造の酒造りを担っていた杜氏が腰を痛めて引退することになり、まだ蔵に入って1年程度の吉田真子さんが杜氏代理となります。
「ありえないですよね。県内でも“あの蔵、大丈夫か”って思われていたと思います(笑)不安はありましたが、やるしかないって覚悟を決めてからは気持ちが楽になりました」

“頑張りすぎない努力”で、トンネルの先に光が見えた
今でこそ、酒蔵のオーナー自らが杜氏となり、酒造りをすることも珍しくありませんが、基本的に蔵の経営と酒造りは別。ただでさえ慣れない仕事を吉田真子さん一人ですべて担うのは想像以上の激務でした。酒造りが始まれば、早朝から蔵に入り、夜中も3時間おきに麹の温度をチェックするなど、満足に眠れない日々が半年間も続きます。吉田真子さんは蔵のハードな労働環境に心身ともに限界を感じ始め「もう蔵に入るのもイヤだ」そんな風に思うほど、追い詰められていました。
見かねた母の由香里さんは、ちょうど試験醸造が始まった北海道上川郡の新設蔵「上川大雪酒造」で研修をするよう吉田真子さんを説得。そこで吉田真子さんは名杜氏・川端慎治氏と出会い、教えを受け、初めて酒造りの楽しさを知ったといいます。それまでの吉田真子さんの酒造りは「麹が36度になったら手入れをする」「39度になったらもう一度」というように、教科書通りのやり方をしていましたが、川端さんから教わったのは、手の感触、湿気の感じなど五感を使った酒造りでした。麹は生き物。気圧や湿度は毎日変わり、米も年によって違うため、毎回同じことをしても仕上がりは安定しません。だからこそ川端さんは知識だけに頼るのではなく、感覚を覚えることを吉田真子さんに伝えたのでした。

川端さんから学んだことは酒造りだけではありません。ゼロから日本酒の世界に飛び込み、余裕のなかった吉田真子さんに川端さんが語ったのは「頑張りすぎない方がいい。力の抜き加減を覚えなさい」ということ。
「今思えば、その時はちゃんとしなきゃって思いすぎて無駄なこともたくさんしていたんです。強弱の付け方が分かっていなかったんですね。川端さんにそう言われてようやく肩の力が抜けました」
それからの吉田真子さんは、「任せられることは人に任せる」「すべての工程を100%の力でやらず優先順位をつける」など、“頑張りすぎない努力”を始めました。その後、福井に戻った吉田真子さんは正式に杜氏に就任。当時24歳の最年少女性杜氏として注目を集めました。

目指す方向が決まれば迷いは消える
吉田真子さんが杜氏に就任した年、姉の祥子さんも夫と共に帰郷。一家で蔵を切り盛りしていく体制が整いました。家族の支えがあるとはいえ、蔵を背負う吉田真子さんのプレッシャーは相当なもの。
「1本目が出来上がるまでは眠れませんでした。飲めるお酒がちゃんとできるのか、本当にドキドキで。腐造※3になれば大きなタンクに入っているお酒はすべて廃棄になりますし、できたとしてもこれまでうちのお酒を飲んでくださった方に受け入れられるかも不安でした」
そんな吉田真子さんの心配をよそに無事、その年の吉田酒造の看板商品「白龍」が完成。評判も良く、吉田真子さん自身も「80点」と自己評価するほどの出来でしたが、それでも課題は山積みでした。
※3 腐造:醸造の工程でアルコールに強い火落ち菌などの雑菌が侵入し、繁殖し飲めなくなること

1番の課題は、先代の智彦さんが逝去した後、短期間で杜氏が何度か変わった時期があったり、吉田真子さん自身も経験が浅かったことから、白龍の「目指す味」が定まっていなかったこと。家族で話し合い、やはり吉田酒造1番の特徴である米作りからこだわっていることから「米の旨味がしっかりと感じられる酒」というコンセプトに方向性が決定し、造る酒はすべて純米酒に。さらに米は永平寺町産のみとし、その半量は自社米で、米も水も土もすべて土地のものを使う「永平寺テロワール※4」を追求しています。
「酒造りは完成までのたくさんの工程で、都度決めなければいけないことがあります。思い通りにいかなくて、いくつも変更すると、結局どこがよくてどこが悪かったのか分からなくなってしまうことがありました。また、私の未熟さに、色々な方が心配してアドバイスをくださるのですが、蔵によってやり方が違うので混乱してしまっていました。でも方向性さえしっかりと決めれば、情報の取捨選択ができるようになり、ぐっと楽になりました」
※4 テロワール:ワイン、コーヒー、茶などにおいて生産地の土壌、地勢、気候、人的要因などによって形成される特徴

それでも理想とする酒質には後一歩足りず、「テロワール」を謳うには、土や米の個性を表現しきれていないと吉田真子さんは言います。長い道のりではありますが、昔のように肩肘を張って頑なに頑張るのではなく、目指す理想に向かって楽しんで酒造りに取り組んでいます。
大変なことの多い杜氏という仕事の中で一番嬉しい瞬間はと尋ねると「やっぱりお客さまに“美味しい”と言っていただけた時です。私自身、日本酒の美味しさに目覚めたのは、食事とのマリアージュだったので、うちのお酒は食中酒を意識しています。日本酒が苦手という人にも楽しめる提案をどんどんして、白龍が日本酒を好きになるきっかけになれば嬉しい」と笑顔で答えてくれました。
現在は日本酒の価値を海外でもっと高めていこうと香港の企業と合弁で事業をスタートさせた吉田真子さん。若き杜氏の未来に、多くの日本酒ファンが期待しています。
MAKO YOSHIDA's Recommended items
吉田真子さんのお気に入りアイテム


酒蔵の中は湿度が低い場所もあり、乾燥が気になるという吉田さん。さらに酒造りの時期は、とにかく忙しくて睡眠不足になりがち。
「精神的にも休まるときがないので、肌にはとても過酷な環境です。しっかりスキンケアをしなければと思いながらも、1分でも長く寝たいので、あまり時間をかけられないのが悩みでした。でも、レジュアーナのクリーム イン ミルクは、1本でクリームまでしっかり塗ったかのようなリッチな使用感でとても気に入りました。乳液ってベタつくことが多くて苦手意識があったのですが、印象が変わりましたね。さっぱりしていて肌馴染みがいいので、これなら毎日使いたいです。
あとは、アクネグランのコンセントレート ジェルスポッツは、透明でサラッとしていてメイクの上から使えるのもいいですね。仕事柄、どうしても香りに敏感なので、どんなにいい商品でも香りがきついと使えないのですが、ナリスさんのスキンケアはどれも無香料なので、気持ちよく使えました。これからも使い続けたいです」